異なる背景を持つ人たちによる学び合い
樫村 西尾さんはワークショップやイベントを開催される時に、いつも全学メールを送られてますよね。先端芸術表現科(以下、先端)にいらっしゃいながら、学生を広く募集していることにとても興味があります。その辺りは、どういう考えを持ってらっしゃるんですか?
西尾 ありがとうございます。着任当初から全学メールを送ってるんやけど、その背景には先端に対する思いと、僕が美術とかアートプロジェクトに対して思ってることの両方があります。
先端の学生は本当に興味の幅が広いので、専門に特化した知識や技術は他の科の学生の方が優れているという状況です。そんな中で、先端の学生にしか見えていない景色や視点もあるんじゃないかと思った時に、学生同士が交流できると藝大としてももっと面白くなるんじゃないかという思いがひとつです。
もうひとつは最近『美術は教育』という本を出版したんですけど、教育は異なる背景を持った人たちが学び合うのが重要かつ一番の面白みだと思っているので、できるだけいろんな背景を持った人と交われるように、他の科に広げていきたい思いがあります。
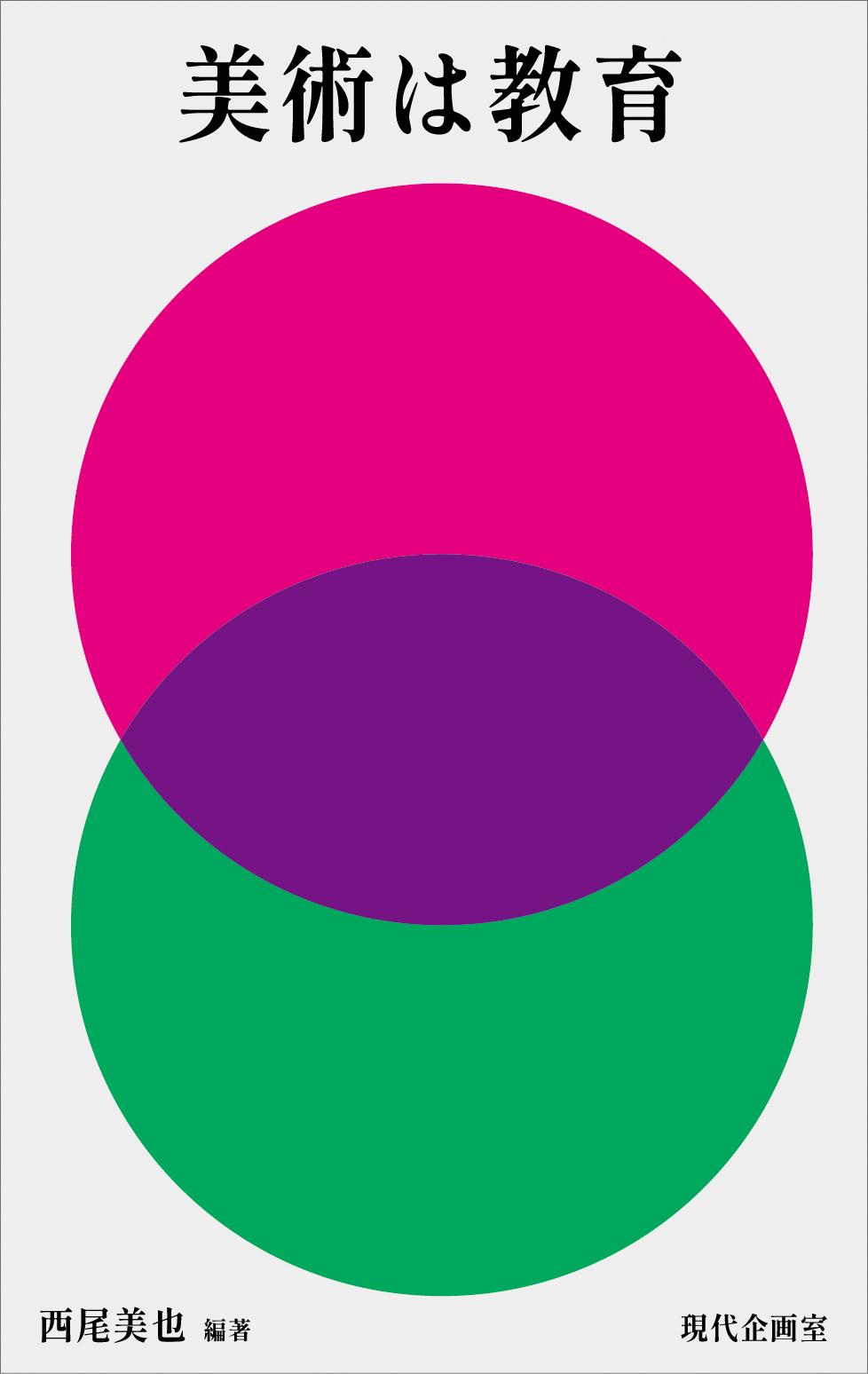
樫村 私も8月にウガンダで9日間のワークショップを行ったんですが、西尾さんにラブコールをして初めて先端の学生2人を交えました。短期間でいろんなフィールドの人が混ざり合うワークショップの特性上、予定調和にしたくないと思っているんですが、それぞれが自分の専門性と興味をかなり強く持ちながらも、やりたいことが具体的に決まっていたわけではなかったので、何をやってくれるのかとても楽しみにしていました。
結果、とても建築の学生では思いつかないような、当初から周りの人たちを巻き込みながらやっていくことを見せてくれました。先端の学生は専門性や興味が広いぶん、とにかくやりながら「これだ」というものを発見して、それを育てるところを磨く学科なんだなというのが見えてきて。来年も一緒にやりたいと思いましたね。

でもやっぱり9日間はとても短いですよね。例えば1年間のカリキュラムとか10日間のワークショップでは、できることの感覚はそれぞれ違ったものがあると思います。
西尾 そういう意味では大学だと4年間、大学院だと2年間の教育があるわけですけど、それを樫村先生自身はどう捉えているのか聞いてみたいです。ご自身の分野を教育していくときに、自分で実践することと教育することは違った面があると思うんですけど、どういうふうに折り合いをつけていますか?
樫村 私個人としては、あんまり机の上だけで終わらせたくないとずっと思っています。例えば大学院の2年間のうち1年目は実物を作るようにしています。そのために規模を小さくしたり、人数を増やしたりする工夫が必要ですが、模型で終わりではなく建築が立ち上がったときの複雑さみたいなもの、それこそが面白いのだということをやっぱり感じてほしいんです。
翻って設計する段階でもう一度紙に戻ったときに、その複雑さをどう予測しながら超えていけるだろうと考えるような循環が起きてほしいですね。なので2年目はそれぞれが自分の興味にもう一度立ち戻って考えていくふうにしています。
西尾 樫村研究室は建築設計という研究室でしたっけ。建築設計をする人間を育てる前提があって、そのために1年目は作ることが大事だという順番ですよね。そこがある意味うらやましいというか。先端の場合は本当に専門性が何もなく、完全に自由になっている現状なので、指導や教育というものの不可能性に直面しまくりですよね。

樫村 アーティストを育てるということではないんですか?
西尾 科としてはアーティストだけでなく、アーティストを支える人や起業していく人がいてもいいよねという考えです。
樫村 建築科では長年「建築家を育てる」ことを大きく掲げています。それは他の科と比べてもめずらしくて。「じゃあ建築家って何?」というふうになるんですけど。でも藝大の中だからこそ建築家であることをむしろ打ち立てることで、ものを作ることをちゃんと真摯に見つめることに繋がるんじゃないかと私は思っています。もちろん高い専門性も求められるので、卒業後もたくさん勉強しなくちゃいけません。だからといって大学で知識だけを詰め込んで、建築が立ち上がったときの面白さに立ち会えないのは違うよなという気がしていて。
なので他の科の人たち、特にものを作るということを拡張して考えている人たちと一緒にやることで、建築がものを作るだけじゃなくて、環境を読み解いたりする時にも専門性を広げていける可能性を感じています。ものを作るだけじゃない建築家もすごく増えてきていますし、それこそ美術館の空間の演出をしたり、建築の定義はかなり広がってきています。もしかしたら学生にとっては、それが普通の事になりつつあるのかもしれないですね。
ーー専門がない先端はある意味で貴重なのかもしれませんね。
西尾 ある程度自分が得意とするメディアでやってきた上で、もう少し俯瞰的に見たり、別のものと繋げて考えたりしたい人たちが先端にいますし、先端の教育方針も、それまでやってきたことをそのままやってたら大体否定するんで、違うふうに転換したり、何か新しく挑戦したりすることをこちらも期待しています。でもそれって何でしょうね。
樫村 西尾さんも教えることで、逆に学ぶこともあるんですか?
西尾 そうですね。学び合いという意味では、全然考えようとしてなかったテーマが学生から出てくるので、深い議論ができるわけではないんですけど、こちらも勉強しようとしたり、知りたいと思ったりするようになる。あるいは学生の話が分からなかったら、相手が分かるように言えることが大事だよと伝えています。社会の中で生きていくことは結局そういうことですよね。自分がめっちゃ楽しいと思ってることを専門の中だけで喋るのではなくて、自ら翻訳して実践していったり、理想とは離れるけど新しい展開になるかもしれない偶然性を自分のものにしていく技術だったり。それは大切かなと思っています。

樫村 今回のウガンダでも、先端の学生たちのやろうとしているアイデアをどういうふうに育てるべきか、立ち止まって考えた瞬間がありました。建築の学生たちのことはよく知っているので、アドバイスもしやすいんですけど。やってみないとわからないものに対して、どう接すると彼らの持っている種が花開くのか。
様子を見ながらお互いやってたんですけど、私も知ってることばかりを上から教えるのだと、さっき言われていた思いも寄らなかったことが出てこない。自分がどうアドバイスすべきかと考えてたんですけど、建築の学生と先端の学生同士がかなり言い合いをしながら育っていく状況がありました。言い方も「そうしたらいいんじゃない」?っていう優しいものではなくて、「何やっちゃってるの?」と言い合ってる状況で。それがむしろうまくいってるんだなと思ったんですね。
立場の話でもないんですけど、「これだ!」と閃いた状態をどう導いてあげるのか、とても難しいけど、大事なんだろうなと気づきました。
ーー9日間という短い期間と1年間という期間だと育て方も全然変わってきそうですよね。
樫村 1日や2日だとまた違うかもしれませんが、1週間だと何かしら未消化の部分は残るのは当然だとも思っています。だからこそ「あれは何だったんだろう」と、長期間自分の中で振り返ることができる。それはもう「なんだったんだろう」とはっきり分からなくても、何かを体感してること自体がいいことだなと。
面白いことに未消化のままだと、その後に学生たちが議論したがるんですよ。浅い話で終わってたところは「あれはこうだったんじゃない?」と話し合って、「じゃあ今度はこうしてみよう」と発展させていくので、俯瞰してる私としても良いものだと捉えています。
未消化をくだき続ける過程で
ーー未消化なものが制作の種になることもあると思うんですが、お二人にとって現在、何か未消化なものあるのか気になりました。
樫村 大体未消化ですね。建築をやってて、特にヨーロッパやアメリカだとサステナビリティとかエコシステムが、当然かつホットな話題として議論されているにもかかわらず、やっぱり日本は遅れていると感じます。もちろん長い建築のプロジェクトだと雨水をどう利用するのか、電気をどう抑えるのか計画して進めていきます。日本ではかなり高度なシステムや制度が整ってきているのに、やっぱり生活の中で浸透してないと見受けられるのは、なんなんだろうと考えているところですね。
浦安藝大でも、浦安というフィールドでそういったことを考えられないかと思っています。日本はすごく整っていて、例えばゴミを捨てたら臭いがしないところまで行くとか、蛇口をひねれば綺麗な水がでできて大抵飲めるとか、快適だからこそ見えなくなっているもので、意識が遠のいてることを1年ごとにテーマを少しずつ変えながら、建築で回答していきたいです。

西尾 未消化やからずっとやってるのはあると思います。服も似てる部分があって、生活と芸術の関係というのは常に考えています。生活は生きている以上つきまとうので、「これで完璧」というのはないという意味で、未消化のまま考えて実践を重ねています。ファッションの業界としての分野と、アートとしてのそうじゃない服の在り方がなかなか交わらないことは、ずっと思い続けてることですし、一方では明らかなファッションは環境問題とかいろんな問題がある産業やのに、なかなかやめられない。それに関わる人口が多すぎて、見直すと失業者がとんでもなく増えることを考えると、なかなか構造を変えられないというか。アートはあんまりそういう問題と関係なく、服の在り方について面白いんじゃないと言えるけど、そこをどう折り合いをつけていくかは、正直大きな課題だろうなと。
可能性のひとつとしては、本当に夢のような話ですけど、服を着る多くの人が、その違和感に気づいてじわじわと従来のファッションの在り方から退散していくこと。服は毎日着てるものなので全員が見直したら、お金の稼ぎ方とか暮らし方自体の概念が変わっていくこともあり得るかもしれません。それを浦安で実現したいわけじゃないですけど、暮らしの中でみんなが考えられるようにする、というコンセプトは通じるものがあると思います。

樫村 いま、暮らしや生活とおっしゃったのが印象的だったんですけど、暮らしの中の洋服の在り方って、洗濯したり干したりアイロンかけたり古いものを見直したり、着るだけじゃない様々なことがあるじゃないですか。
今回のウガンダでもワークショップをした敷地に井戸があって、みんなが洗濯しに来るんですね。学生が作ったものにも洗濯物をかけてもらったらいいんじゃないかと、洗濯紐みたいなものを残してきました。そういった着るだけじゃない服にまつわるものを、西尾さんはどういうふうに捉えてらっしゃるんですか?
西尾 まさにそこが「拡張するファッション」が射程にしている部分です。服を手に入れるところから捨てるところまでの間に、いろんな服との関わりがあります。そこをいろんな形で組み替えてみることで、考えを促すということをやりたいなと考えています。
暮らしや生活というときに、最近「日常美学」に関する新書(※)が出版されたんですが、普通の暮らしを美学として捉えるというコンセプトで、それ自体がかなり新しい考え方みたいです。これまで美学というと、西洋の芸術にものをどう感性学として言語を与えていくかが中心でした。それが社会の構造の変化や、これまで排除されてきた女性の視点とかが反転してきたときに、日常の中にある洗濯の行為とか食事を作る行為に、美学というものがこうも切り込めるのかと。まさに拡張するファッションでやりたいことに通じていると思いました。
※「『ふつうの暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』青田麻未著
暮らしの根源と便利さのあいだ
樫村 ちなみに洗濯機ってどうですか?
西尾 僕はアフリカのケニアに滞在していた頃に手洗いの洗濯の風景をずっと見ていて、干された光景も含めて行為全体がすごく美しいなと感じてました。なので洗濯機はやっぱり便利さがある一方で、今だと乾燥まで全部やっちゃうから、服が街の中にある風景を奪ってると考えるとすごくもどかしいですよね。それを使い分けられたらいいなと思うんですけど。
樫村 そうですね。建築や設備もまさにそのものじゃないかと思っていて、便利だし、広告でも新しくて革新的だと謳って買わせるじゃないですか。やっぱりそれを手放すのは価値観を大きく変えないと難しくて。もちろん手洗いも面倒くさいし、ボタンひとつで済ませたいと思う瞬間もあるんですけど。めんどくさいんだけど干してみると、なんか気持ちいいことだったり。労働であり、生活の一部ではあり、でもそれが日常風景として美しくもあるものが、かつて三種の神器と言われていたものによって奪われてるんだと気づくフェーズにいくのは難しいことだと思います。
でもそれがやっぱり建築の場合、エアコンも電気もそうだし、あらゆるものに関わってきます。原始的なところに立ち戻ろうと言いたくないんですけど、大学で建築をやっているところに、それに気づく機会があったらいいなと思っています。
西尾 去年「拡張するファッション演習」でお招きしたファッションデザイナーの居相大輝さんという方がいるんですけど、そういう意味での生活に対する美意識がすごく高い人です。彼は兵庫県の山奥でセルフビルドの家で暮らしていて、その場所で採れる植物で染めた布で服を作っているんです。セルフビルドの家には五右衛門風呂もあれば、ボタンひとつでガス焚きできるお風呂もある。両方の選択肢を持てる家を作って暮らしを実践していて、まさに今の話と通じると思いました。

服の話でも、生活するのは自分たちのはずやのに、すでにある与えられた機能とかサービスに乗っかって、受け手になりがちじゃないですか。そんな中で、例えば藝大やと場合によっては服を素材から作ることもできる。そんなふうに原理的で改革的な精神で語ることもできるけど、もう少しDIYの精神とか、自分でできることはやろうよみたいなところに落とし込むこともできるじゃないですか。
アフリカやと家をほんまにみんなで建てたりしますよね。そういうときに専門家として建築物を作ることと、誰もが作れるようになっていく社会の理想のバランスは、樫村さんの中でどうお考えですか?
樫村 選択できることについて、私も同じようなことを考えています。ウガンダで日本食レストランを建てた時にユーカリ材を使ったんですね。ユーカリ材は元々オーストラリアから入ってきた樹種で、とても早く育つので一般に流通してるチープな木材なんです。なので、ウガンダでも結構見下されていて、屋根の構造にも使うんですけど、見えないようにモルタルで仕上げてペンキを塗って隠すんですね。じゃないと「あの人のうちはお金がないんだな」という見方をされるからです。そんなユーカリ材を使った時に、繋ぎの部分にいわゆる原初的なロープで縛る選択肢もあったんですが、それをやってしまうと、その場所では自然じゃない状態だったんですね。

というのも、建てた場所がまあまあ都会のエリアで、ガラスもあるし、鉄もあるし、それこそエアコンのついてるオフィスもある場所でした。メンテナンスをできる人がそんなにいない状況で、あえてロープで縛ることが不自然だなと思って、繋ぎの部分は鉄で溶接をするジョイントを入れることを選択しました。
なので主構造である木材は原初的でもあると解釈もできるものを持ちながらも、強度を担保するものに対しては、きちんと近代の技術と素材を共存させる選択肢をとったというのがその時の判断でした。もちろん、どちらかだけを選ぶことはできたんですけど、どのバランスをとるべきだろうかを場所によって判断するのが今の状況なのかなと思います。
西尾 ウガンダの建築家の育成状況はどんな状況なんですか?
樫村 ウガンダの場合は建築のライセンスをとっている人はまだまだ少なくて、取れるとステータスになる状況です。やっぱり無名の大工さんたちが作ってることが多くて、構造的にも危ないので倒壊事故が起こったりする状況が長らく続いてました。そんな中で1960年代に独立した後に海外に留学して世界の考えに触発された人たちが現地に帰ってきたり、長く植民地化されていたので、イギリスやオランダ、ドイツの建築家と、たまに私みたいな日本の建築家との意見交換したりが影響して、大学でも設計やデザインとは何か?といったことを教えるようになっています。
今回は現地の学生も一緒に制作したんですけど、まさにサステナビリティに関してどう考えるのか、屋根の素材はなぜこれなのかという話が出てきていて、面白くなってきたぞと感じてますね。
西尾 それこそさっきの選択肢のある考え方できる人がいるのが、成熟した社会のひとつの見本だなと思っていて。現地でこそ、そういう人が育っていくと非常にいいんでしょうね。
(前編終わり)▶︎続きの後編はこちら



